
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】8 枝ニです
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はコメントやお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
クリックできる目次
弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】8
【特許・実用新案】8
優先権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。
(イ) 甲は、特許出願Aをした後に、出願Aを優先権主張の基礎とした国内優先権の主張を伴った特許出願Bをした。その後、甲は、出願Aについて、出願審査の請求を行い、出願Aの出願日から1年経過前に、出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、出願Bについて、出願Aに基づく国内優先権の主張の効果が認められない。
(ロ) パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国Xにおいて最初の特許出願Aをした。甲は、出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って、日本国において特許出願Bをした。その場合であっても、出願Aの出願日から1年以内であれば、甲は、出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って、日本国において、さらに特許出願Cをすることができる。
(ハ) パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国Xにおいてした特許出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って日本国に特許出願Bをした。この場合において、甲が、経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、優先権証明書類等を提出したものとみなされる場合がある。
(ニ) 故意でなく優先期間内にその特許出願をしなかった者が特許法第 43 条の2に規定するパリ条約の例による優先権主張の手続を行う場合、その責めに帰することができない理由によりこの手続をすることとなった者を除いて、この手続に関する手数料を納付する必要がある。
(ホ) 甲は、特許出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、出願Aに基づく国内優先権の主張を伴った特許出願Bをした。この場合、特許庁長官は、甲に弁明書を提出する機会を与えた後に、出願Bを却下するものとする。1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝ニ
(ニ) 故意でなく優先期間内にその特許出願をしなかった者が特許法第 43 条の2に規定するパリ条約の例による優先権主張の手続を行う場合、その責めに帰することができない理由によりこの手続をすることとなった者を除いて、この手続に関する手数料を納付する必要がある。

不責事由、正当理由、故意ではないとか・・・・苦手なんだよね・・・

改正の箇所は狙われやすいですよね。
原則と例外でざっくり覚えると分かりやすいかも。
とりあえず条文から。
(パリ条約の例による優先権主張)
第四十三条の二 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。ただし、故意に、優先期間内にその特許出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

特許法43条の2により、「故意でない場合は救済される」が原則と言えますよね。
ざっくりとは、故意で無ければ救済。でも手数料がいる!ってことです。

条文に手数料のことは書いてないよ?

そうですね・・・確かに。
こちらの特許庁のサイトでどうでしょう?
1.概要
令和5年4月1日付でその一部が施行される、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)により、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと(以下、「故意でない基準」という。)」に緩和されるとともに、回復手数料の納付が必要になります。
(省略)
2.故意でない基準の対象となる手続
○対象手続(全18書類)及び手続書面における権利の回復に係る手続である旨の記載方法一覧
(3)パリ条約の例による優先権主張(特許法第43条の2)
(省略)
5-1.回復手数料
故意でない基準により回復理由書を提出する際には、回復手数料を納付しなければなりません。
- 特許 212,100円
- 実用新案 21,800円
- 意匠 24,500円
- 商標 86,400円
- 「故意によるものでないこと」による期間徒過後の救済について | 経済産業省 特許庁

ほんとだ。
回復手数料、特許で20万円近くいるじゃん!
めちゃくちゃ高いんだね!?

そうなんです。これで記憶に残りますね(笑)
で、原則は上記の通りだったのですが、例外があって、不責事由アリの場合はどうするかってことなんだけど。
それも同じサイトに記載があるのです。
5-2.回復手数料の免除のための手続
手続期間内に手続をすることができなかった理由について、手続をする者の責めに帰することができない理由※(以下、不責事由という。)があり、かつ、その事実を証明する書面により不責事由が確認できる場合は、回復手数料が免除されます。

不責事由ある場合は、回復手数料が免除されるのです!
さっき見たとおりめちゃくちゃ高いしね・・・まあ不責事由あるなら許してあげるかって感じなのかもしれませんよね。

なるほど!

結局、故意でなければ救済されるが、お金(回復手数料)は必要。
ただし、不責事由があればお金不要ってことだね。
なので、この選択肢は○となります。

わかったよ!
最後に、「不責事由、正当理由、故意ではない」ざっくりでいいからわかりやすく教えて!

ざっくりとしたイメージはこんな感じ。
不責事由(一番厳しい、天災(地震・洪水)とか不可抗力レベル)
正当理由(真ん中くらい、合理的な説明がつく状態)
故意ではない(一番緩い、うっかりミスも入る)
問題:(ニ) 故意でなく優先期間内にその特許出願をしなかった者が特許法第 43 条の2に規定するパリ条約の例による優先権主張の手続を行う場合、その責めに帰することができない理由によりこの手続をすることとなった者を除いて、この手続に関する手数料を納付する必要がある。
答え:○
理由:故意でなければ救済されるが、お金(回復手数料)は必要。
ただし、不責事由があればお金不要のため
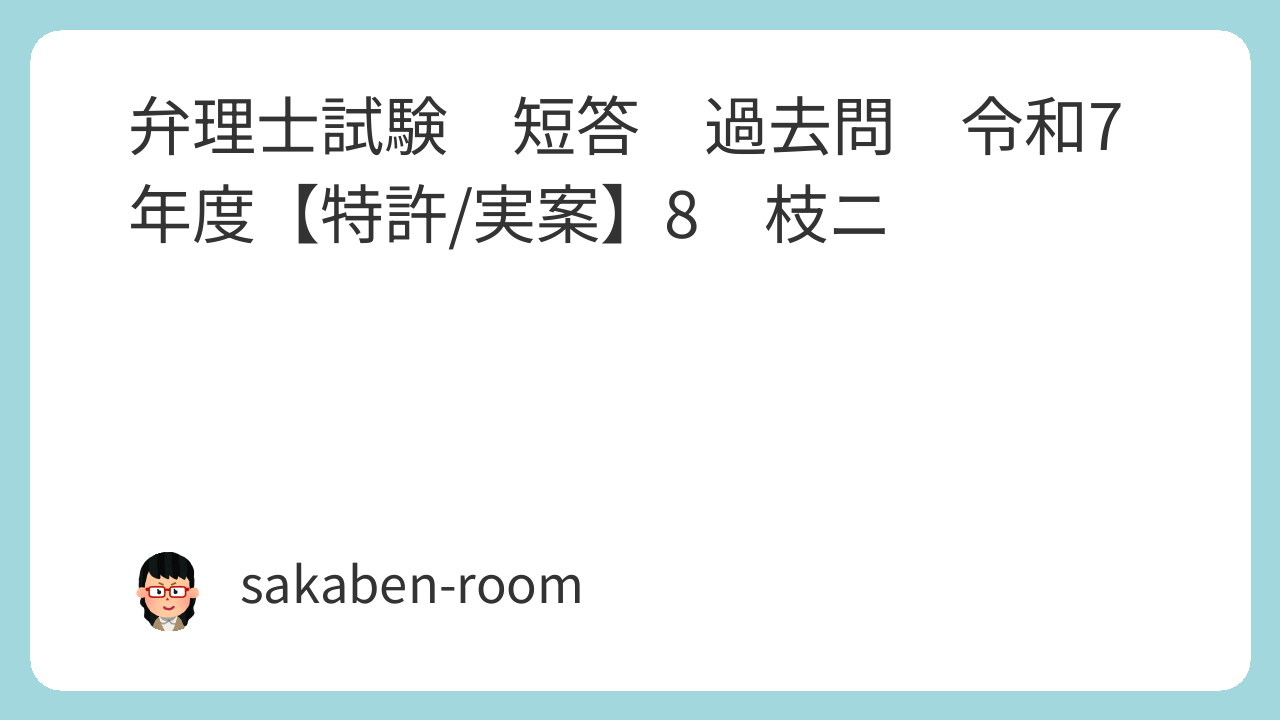
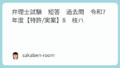
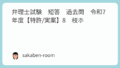
コメント