
弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】8 枝ロです
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はコメントやお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
クリックできる目次
弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】8
【特許・実用新案】8
優先権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。
(イ) 甲は、特許出願Aをした後に、出願Aを優先権主張の基礎とした国内優先権の主張を伴った特許出願Bをした。その後、甲は、出願Aについて、出願審査の請求を行い、出願Aの出願日から1年経過前に、出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、出願Bについて、出願Aに基づく国内優先権の主張の効果が認められない。
(ロ) パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国Xにおいて最初の特許出願Aをした。甲は、出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って、日本国において特許出願Bをした。その場合であっても、出願Aの出願日から1年以内であれば、甲は、出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って、日本国において、さらに特許出願Cをすることができる。
(ハ) パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国Xにおいてした特許出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って日本国に特許出願Bをした。この場合において、甲が、経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、優先権証明書類等を提出したものとみなされる場合がある。
(ニ) 故意でなく優先期間内にその特許出願をしなかった者が特許法第 43 条の2に規定するパリ条約の例による優先権主張の手続を行う場合、その責めに帰することができない理由によりこの手続をすることとなった者を除いて、この手続に関する手数料を納付する必要がある。
(ホ) 甲は、特許出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、出願Aに基づく国内優先権の主張を伴った特許出願Bをした。この場合、特許庁長官は、甲に弁明書を提出する機会を与えた後に、出願Bを却下するものとする。1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝ロ
(ロ) パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国Xにおいて最初の特許出願Aをした。甲は、出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って、日本国において特許出願Bをした。その場合であっても、出願Aの出願日から1年以内であれば、甲は、出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って、日本国において、さらに特許出願Cをすることができる。

出願Aを基礎でパリ優主張して出願Bてのと、出願Aを基礎でパリ優で出願Cてのをできるかってことだよね?

はい、そうです。

できるんじゃないかなあ・・・
A→B→Cみたいな累積主張が禁止されているだけだったよね??

はい、できるはずです!
累積主張は禁止というより、累積主張してしまったら、優先権が認められないということになります。
パリ条約の根拠条文は4条。長いので関係する部分だけ。
第4条 優先権
- (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。
(3) 正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。- すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。
- (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
(2) 優先期間は,最初の出願の日から開始する。出願の日は,期間に算入しない。
(3) 優先期間は,その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは,その日の後の最初の就業日まで延長される。
(4) (2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は,先の出願が,公衆の閲覧に付されないで,かつ,いかなる権利をも存続させないで,後の出願の日までに取り下げられ,放棄され又は拒絶の処分を受けたこと,及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として,最初の出願とみなされ,その出願の日は,優先期間の初日とされる。この場合において,先の出願は,優先権の主張の基礎とすることができない。パリ条約 | 経済産業省 特許庁

・同盟国民=甲による同盟国=Xへの特許出願=A
・正規の出願=A
・最先の出願=A
なので、優先権の発生要件を具備しています。
そして、Aから1年以内に、Aを基礎としてCは時期的要件も満たすため可能であると考えられます。
ですので、出願Aの出願日から1年以内であれば、甲は出願Aを基礎として日本に 出願Bと出願Cの両方 を行うことが可能であると思います。

なるほど
- 答え ○
- 理由 パリ条約4条A、Cにより可能
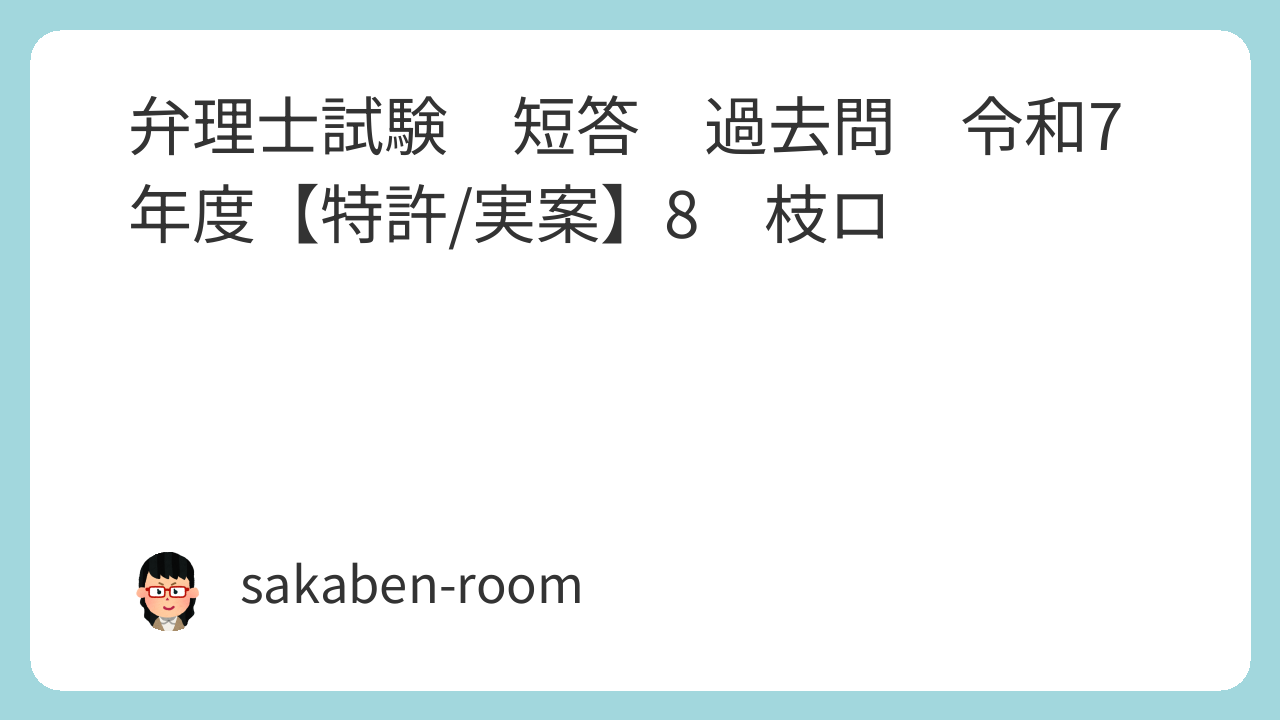
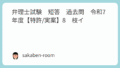
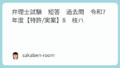
コメント