
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】3 枝1 です。
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はコメントやお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
クリックできる目次
弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】3
【特許・実用新案】3
特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び同法第39条(先願)に関し、
次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係
る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、先の特
許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願
ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、出願公開が行われ、出願審査の請求がさ
れ、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、特許出願について補完
をすることができる旨の通知がなされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる
優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新案登録出願についても同様とする。
1 甲は、発明イ及びロをし、特許請求の範囲に発明イを記載し、明細書に発明イ及びロ
を記載した特許出願Aをした。甲は、出願Aの一部を分割して特許請求の範囲に発明ロ
を記載し、明細書に発明イ及びロを記載した新たな特許出願Bをした。甲は、出願Bを
実用新案登録請求の範囲に発明イと同一の考案イを記載した実用新案登録出願Cに変
更した。その後、甲は、出願Aについて出願審査の請求をした。この場合、特許庁長官
は、特許法第39条第6項の規定に基づいて、相当の期間を指定して、甲に対し、協議を
してその結果を届け出るべき旨を命ずる。
2 甲は、発明イ及びロをし、外国語書面に発明イ及びロを記載した外国語書面出願Aを
し、発明イのみを記載した外国語書面の翻訳文を提出した。その後の日であって、出願
Aが出願公開される前に、乙は発明ロをし、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出
願Bをした。出願Aが出願公開された場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範
囲の先願とする拒絶の理由を有する。
3 甲は、考案イ及びロをし、実用新案登録請求の範囲に考案ロを記載し、明細書に考案
イ及びロを記載した実用新案登録出願Aをした。その後の日であって、出願Aについて
の実用新案掲載公報が発行される前に、乙は、考案イと同一の発明イをし、特許請求の
範囲に発明イを記載した特許出願Bをした。出願Aについての実用新案掲載公報が発行
された場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有
する。
4 甲は、発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Aをした。乙は、発
明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを、出願Aの出願日と同日に
出願した。この場合、出願A及びBのいずれかについて出願審査の請求がなされていな
いときは、特許庁長官は、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき
旨を甲及び乙に命ずることができない。
5 甲は、発明イをし、発明イを学会にて発表した。その発表を見た乙は、明細書の背景
技術の欄に甲による発明として発明イを記載し、特許請求の範囲に発明ロを記載した特
許出願Aをした。その後の日であって、出願Aが出願公開される前に、甲は、特許請求
の範囲に発明イを記載し、特許出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aをいわゆる
拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有する。
1
1 甲は、発明イ及びロをし、特許請求の範囲に発明イを記載し、明細書に発明イ及びロ
を記載した特許出願Aをした。甲は、出願Aの一部を分割して特許請求の範囲に発明ロ
を記載し、明細書に発明イ及びロを記載した新たな特許出願Bをした。甲は、出願Bを
実用新案登録請求の範囲に発明イと同一の考案イを記載した実用新案登録出願Cに変
更した。その後、甲は、出願Aについて出願審査の請求をした。この場合、特許庁長官
は、特許法第39条第6項の規定に基づいて、相当の期間を指定して、甲に対し、協議を
してその結果を届け出るべき旨を命ずる。

めちゃくちゃ難しい・・・どこから手を付けて良いのか(泣)

これは難しいね(涙)
1つずついくしかないよね。
ざっくりとは、特許出願A(イ)→分割出願B(ロ)→実案出願C(イ)→同日出願の協議命令がくるか?ってことだよね。

えっと、まず分割を基礎で実案への出願変更ってできたっけ?

そのあたりから条文を確認しましょう。
特許→実案への変更なので、実用新案法ですね。
実用新案法10条1項
(出願の変更)
第10条 特許出願人は、その特許出願(特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第44条第2項(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第13条第6項において準用する同法第10条の2第2項の規定により特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第10条の2第2項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその意匠登録出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。
3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第3条の2に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第29条の2に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び次条第1項において準用する同法第30条第3項の規定の適用については、この限りでない。
4 第1項又は第2項の規定による出願の変更をする場合における次条第1項において準用する特許法第43条第2項(次条第1項において準用する同法第43条の2第2項(次条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。
5 第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
6 第1項ただし書に規定する3月の期間は、特許法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第2項ただし書に規定する3月の期間は、意匠法第68条第1項において準用する特許法第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
8 第1項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第8条第4項又は次条第1項において準用する特許法第30条第3項若しくは第43条第1項及び第2項(これらの規定を次条第1項において準用する同法第43条の2第2項(次条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
9 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第1項の規定による出願の変更をすることができる。
10 第8項の規定は、第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。

実案10条1項ですね。
かっこ書きのところですが、これは実案→特許出願とした分を除くということです。
つまり、実案→特許→実案への変更は禁止ということですね。

てことは、元々が分割出願であるだけでは、除かれないということだよね?

はい。
元々が分割出願であっても、新たな独立した特許出願なのでOKです。

分かりました!
あとは・・・変更した場合、たしか取下げ擬制されちゃうんじゃなかったっけ?
そうであれば、協議命令の対象になる出願ないんじゃないかと・・・

実案10条5項ですね。
確かに取下げ擬制されるのですが、取下げされるのは分割出願Bであって、特許出願Aはそのまま残るのです。

なるほど
あと・・・出願日はどうなる?

実案出願Cは分割出願Bのときにしたとみなされて(実案10条3項)、さらに分割出願Bは特許出願Aのときにしたとみなされる(特許44条2項)ので、結局、出願日は、実案出願C=特許出願Aとなります
(特許出願の分割)
第44条
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定の適用については、この限りでない。

なので、結局、特許出願A(イ)と実案出願C(イ)とが同日出願として残ってしまうので、協議命令は出る(ハズ)
特許法39条も確認しておきましょう
(先願)
第39条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第44条第2項(第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第2項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
6 特許庁長官は、第2項又は第4項の場合は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第2項又は第4項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

なので、枝1は○ですね!
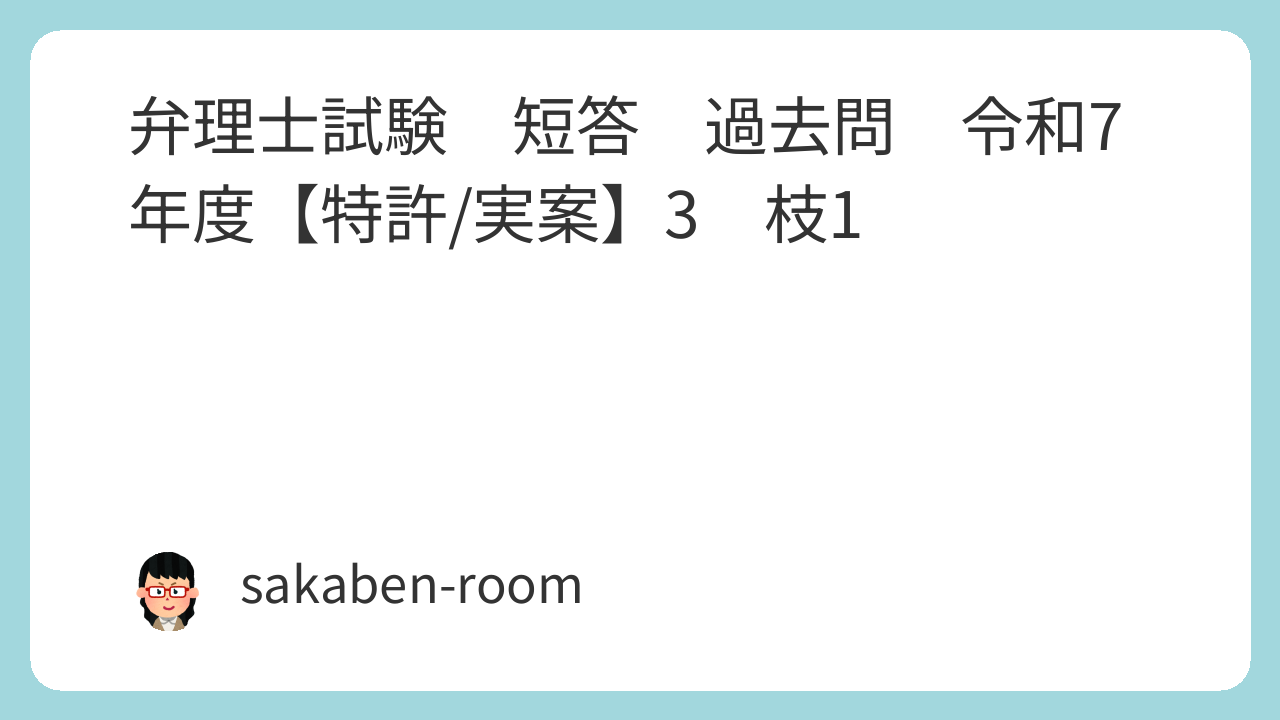
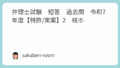
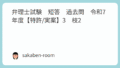
コメント